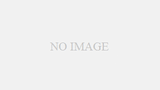*このブログは、僕とChatGPTの会話をもとに作成しています。実際の会話量は少ないですが、読みやすくするために編集を加えています。具体的には、会話の流れを自然に整え、一部のやり取りを補完しています。また、僕の発言は基本的にそのまま残していますが、会話として成り立つようにChatGPTによって生成された部分も含まれています。元の意図を損なわないよう配慮していますが、あくまでエンタメとしてお楽しみください。なお、本ブログに掲載されている内容は正確性や完全性を保証するものではなく、誤りを含む可能性もあります。情報の利用にあたってはご自身でも確認の上、ご判断ください。僕:
パレートの法則って何?
GPT:
パレートの法則(Pareto Principle)は、「全体の結果の80%は、原因の20%から生じる」という経験則で、「80対20の法則」とも呼ばれるよ。
もともとはイタリアの経済学者パレートが「富の80%は20%の人が持っている」と気づいたことから来てるんだ。その後、ビジネスや日常のいろんな場面に応用されてるよ。
僕:
たとえば、成果の80%を出してる20%の部分に絞ったとして、その中のまた20%で同じことが起きるの?みたいな感じ?
GPT:
そうそう、それもパレートの考え方の一つ。
「成果の80%を生む20%」をさらに分析して、その中の20%がまた成果の大半を生んでる…みたいに、階層的に何度も適用できる。
たとえば、売上の64%は、顧客全体の4%が生んでるみたいな結果も出るんだ。
僕:
でも実際には、その80%を削るって、誰かがその分の負担をしてるだけじゃない?
GPT:
そこは現実的な視点だね。
「20%に集中する」って理屈はよく聞くけど、削られた80%の業務やタスクは消えるわけじゃないんだよね。誰かがカバーしてたり、見えないところで回ってたりする。
たとえば、企業が重要な20%に集中したら、雑務やバックオフィスの仕事は誰かがやらなきゃいけないし、フリーランスが「稼げる仕事だけやろう」としても、営業や経理は残る。結局、しわ寄せは出るんだ。
僕:
じゃあ、しわ寄せが出ない例ってあるの?
GPT:
完全にゼロってのは難しいけど、比較的しわ寄せが起きにくい例ならあるよ。
- 無駄な会議を削ってチャットで済ませる
- チャットボットで定型対応を自動化する
- よく売れるデジタル商品だけを残して他を作らない
- 服を毎日同じにして選ぶストレスをなくす(ジョブズ方式)
こういうのは「誰かが困る」というより、無駄をそぎ落として効率化してるパターンかな。
僕:
効率化っていっても、結局ツールとか機械に頼ることが多いよね。でも、それらを作る人やメンテナンスする人も必要だし…その手間まで減らすにはどうしたらいいんだろう?
GPT:
いい視点だね。そこまで突き詰めるなら、たとえば:
- AI自身がプログラムを書いたり修正したりする
- 壊れにくい・メンテフリーな設計にする
- 人は「作る」より「選ぶ・考える」に役割を変える
- そもそも不要なものは作らないって決める
この最後の、「そもそも存在しない」っていうのが、実は究極の効率化とも言える。
僕:
「究極の効率化は存在しないこと」って、東浩紀さんの「タイパの究極は存在しないこと」に近いかもって思った。あれってどういう意味なんだろ?
GPT:
面白いね。東浩紀さんの思想には「観光客の哲学」とか「動物化するポストモダン」みたいな、主体的に何かを作るんじゃなくて、漂う・受け取ることのほうが現代的って話があるよね。
その感覚と、「効率化=存在しないこと」はすごく近い。
- 何かを生むより、そもそも無いほうが楽
- 選択肢が少ないほうが疲れない
- 「やらない」ことが最もエネルギーを使わない
人間が何かを「作る」のをやめて、「ただあるものの中から選ぶ」って方向にシフトしていくと、最終的には「何もしない」が最も効率的って話になるかも。
「パレートの法則って何?」GPTと対話してみた結果…_その2へつづく