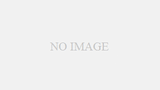*このブログは、僕とChatGPTの会話をもとに作成しています。実際の会話量は少ないですが、読みやすくするために編集を加えています。具体的には、会話の流れを自然に整え、一部のやり取りを補完しています。また、僕の発言は基本的にそのまま残していますが、会話として成り立つようにChatGPTによって生成された部分も含まれています。元の意図を損なわないよう配慮していますが、あくまでエンタメとしてお楽しみください。なお、本ブログに掲載されている内容は正確性や完全性を保証するものではなく、誤りを含む可能性もあります。情報の利用にあたってはご自身でも確認の上、ご判断ください。*前回、パレートの法則について話していた内容の続きです。
前回の内容はこちら「パレートの法則って何?」GPTと対話してみた結果…_その1
僕:なんで東浩紀さんって、「人間が主体的に作ること」より、「流れてくるもの」のほうが大事って考えるんだろ?
GPT:それは、東さんの「郵便的」っていう考え方と関係してると思うよ。
僕:「郵便的」って何?
GPT:ざっくり言うと、「何かを発信しても、それがどう届くかはわからない」ってこと。たとえば、手紙を書いても相手がどう受け取るかはコントロールできないし、SNSの投稿も自分の思った通りに伝わるとは限らない。小説や映画も同じで、受け手の解釈次第。
だから、東さんは「人間が主体的に作る」っていうのは幻想で、実際は流れに任せるしかないって考えてる。
僕:なるほど、確かに今って、ネットで流れてくる情報のほうが影響力ある気がする。個人の意志だけじゃどうにもならない感じ。
GPT:まさにそれ。YouTubeのおすすめとか、SNSのトレンドとか、アルゴリズムに乗るかどうかで全然変わるもんね。
だから東さんは、「自分が何を作るか」より、「何が流れてくるか」や「どう乗るか」のほうが重要だっていう。
僕:あと、昔は「作品を作る人」がすごかったけど、今は「流れてきたものを楽しむ人」がメインっていうのもあるか。
GPT:そうそう。東さんの「観光客の哲学」でも、どこかに根を張って何かを作るより、「観光客みたいに漂う」生き方のほうが自由で面白いって言ってる。
これってつまり、「主体的に頑張って作る」より「流れに身をまかせて楽しむ」ほうが効率的って話にもつながってくる。
僕:ちょっと話が変わるけど…僕、正直あんまり働きたくないんだよね。こういう「流れにまかせる」思想って、仕事にも影響あるのかな?最終的には効率化が進んで、働かなくても生きていける時代が来たりするのかな。まあ…僕が生きてる間には来ない気もするけど。
GPT:うん、その気持ちわかる。実際、効率化やAI、自動化の流れは確実に仕事にも影響を与えてるし、「働かなくてもいい状態」に近づいてるのは間違いない。
僕:そうだよね、今もルーチンワークはどんどん機械がやってるし。
GPT:そう。事務、翻訳、プログラミングの一部まで自動化されてるし、動画編集や文章作成もAIがやる時代。
でも「みんなが働かなくてもいい時代」が完全に来るかって言われると…社会の価値観や制度の問題もあって、すぐには難しいかもしれない。
僕:たしかに、「働かない人」への偏見とかもまだ根強いよね。
GPT:うん、技術的には可能でも、社会の受け皿がまだ整ってない感じ。でも、部分的には実現していくと思う。たとえば、自動収入の仕組みを作ってる人は、すでに働かなくても生きてるし、働くスタイルもどんどん自由になってきてる。
僕:じゃあ、僕みたいに「働きたくない」って思ってる人は、社会の変化を待つより、自分で先にそういう生き方を探したほうがいいのかも?
GPT:そうそう。それこそ「流れに乗る」ってことだよね。AIを使って収益化したり、自動化できる仕事を見つけたり。
「完全に働かない」はまだ先かもしれないけど、「少ない労力で生きていく方法」はどんどん増えてる。だから、東さん的な思想って、現代の働き方にもめちゃくちゃヒントになると思うよ。
僕:
消費者的な振る舞いって、SNSとかYouTube、観光では受け入れられてるのに、労働ではあんまり進まないよね?やっぱりジャンルが違うからなのかな?娯楽と仕事って。
GPT:
うん、それはあると思う。娯楽と仕事は性質が違うから、同じ「消費者的な振る舞い」でも受け止められ方が違うんだよね。
僕:
どう違うの?
GPT:
まず、娯楽って「供給過多」なんだよ。SNSもYouTubeも、みんながコンテンツを出しまくってるから、見る側=消費者がむしろ価値を持ってるの。
観光もそう。楽しむ人がいないと、成り立たないでしょ?
僕:
たしかに。観光地って、来てくれる人がいないと意味ないしね。
GPT:
で、逆に仕事は「供給が必要」なもの。つまり、誰かが作らなきゃいけない。労働って「何かを生み出すこと」だから、「ただ受け取るだけ」では成り立たないんだよ。
僕:
でも、最近ってちょっと変わってきてる気もするよ。たとえば、好きなことを仕事にする人とか増えてるじゃん。
GPT:
そうそう、まさにそれが「労働の消費者化」が進んでる兆しだと思う。
・「好きなことを仕事に」=仕事が娯楽っぽくなる
・「自分が楽しむ」ことでお金が生まれる
・仕組みを作って自動で収益が入る=自分はほぼ働かない
これって、働くんじゃなくて「働くことを消費する」みたいな感じになってきてる。
僕:
なるほど。それって「労働してくれるものを消費する」ってこと?それとも、「働かずに済む自分=消費者に回るのが効率的」って意味?
GPT:
後者の意味だよ。つまり、
「労働を自分でやるより、他人や仕組みにやらせる方が効率的」
って考え方から来てる。「自分が労働者」じゃなくて「労働を消費する側」に回る。
僕:
それって、外注したり、AI使ったり、ツールで自動化したりするってこと?
GPT:
まさにそう。そういうふうに「自分が働かない仕組みを作る」ってのが、「労働の消費者化」っていう状態なんだよね。
僕:
ってことは、今後も労働の消費者化が進めば、働かなくてもよくなる人が増えるってこと?
GPT:
うん。ただし、それは「仕組みを作れる人」か、「その流れに早く乗れた人」だけ。AIや自動化が広がれば広がるほど、「労働する人」と「労働を消費する人」の差はどんどん大きくなると思う。
僕:
じゃあ、働きたくない僕は、「労働を消費する側」に回る準備を今のうちにしておいたほうがいいってことか。
GPT:
そう。それが一番効率的だし、「働かなくていい未来」に向かって少しずつ近づいていける方法だと思うよ。
僕:
一つ前に答えてもらった内容で思い出したんだけど、2番の「仕事の娯楽化」って話、ホリエモンが言ってた「労働・仕事が遊びになる」ってやつと繋がってるのかなって思った。
GPT:
うん、まさにその通りだよ!ホリエモンの「労働が遊びになる」っていうのは、まさに“仕事の娯楽化”を表してる考え方だね。
僕:
やっぱそうなんだ。あれって、単に「楽な仕事をしよう」って話じゃないよね?
GPT:
そうそう。むしろ「やらされる仕事」じゃなくて、「自分が楽しんでやれることを仕事にする」って話。例えば、クリエイターとか起業家とか、自分の興味を軸に動いてる人たちがわかりやすい例だよね。
僕:
たしかに、好きなことを仕事にしてる人って、「働いてる感」あんまりなさそう。
GPT:
そう、それが「仕事と遊びの境界がなくなる」っていう状態。まさにホリエモンが言ってるような「遊びとしての仕事」ってことなんだと思う。
僕:
それって、「労働の消費者化」にも通じるってこと?
GPT:
うん、すごく関係あるよ。「労働の消費者化」って要するに、自分でがっつり働かずに、仕組みやコンテンツを作って“労働を消費する側”に回るってことだから。たとえば、YouTuberがコンテンツをアップして、あとは再生されるのを待つだけ、みたいなスタイルもその一種だよね。
僕:
なるほど、AIとか自動化もその流れを加速させてるってことか。
GPT:
そうそう。面倒な仕事やルーチンはどんどん機械に任せて、人間は“やりたいことに集中できる”ようになっていく。だから、「労働が娯楽になる」ってのは、ホリエモンの考えだけじゃなくて、これからの働き方全体の方向性でもあるかもしれないね。